

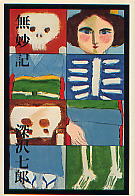


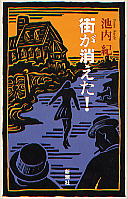

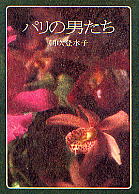
日本人著作(ノンフィクション・フィクション・エッセイ他)−ぱらぶら屋書店目録
| ●Home | ●目録の見方 | ●購入方法 | ●Mail | ●当店案内 | ●店主日誌 |
| 程度A: | 若干のヨゴレやキズがあるがそんなに気にならない程度で、新品に近い本及びほとんど新品本 |
| 程度B: | ヤケ・シミ、ヨゴレ等が多少あるぐらいで、古本という感じを与える程度の本 |
| 程度C: | ヤケ・シミ、ヨゴレ等がそれなりにあり、古本らしい古本 |
注)一部抜粋。詳細は上記●目録の見方へ
・本の部位について
天:本の上部
地:本の下部
背:棚に置いた時に見える、タイトルが書いてある部分
小口:背の反対側のページ部分
 |
 |
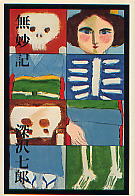 |
 |
| J198 | J202 | J169 | J217 |
 |
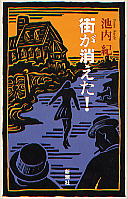 |
 |
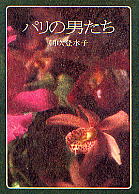 |
| J188 | J013 | J091 | J210 |
| 番号 | 書名 | 著者・訳者・編者 | 出版社 | 発行版 | 売価 (税込) |
状態 | 定価 (税込) |
| J210 画像 |
パリの男たち | 朝吹登水子 | 人文書院 | 1979 初版 |
\600 | 程度A- | \1,300 |
| ●心にくほど、おしゃれで優しく、しかも自ら選んだ仕事に打ち込む、本物の男たち。長い歳月をパリで暮らす女性のヴィヴィッドな男性論。登場人物は、コクトー、マルク・ボーアン、アラン・レネ、トリュフォーをはじめ、お巡りさん、鉛菅工、土建職人、亡命貴族たち、八百屋さん、酒屋さん他。 | |||||||
| J206 | ことばの演芸館(笑いの文章読本) | 池内紀 | 白水社 | 1983 初版 |
\600 | 程度A-、帯 | \1,500 |
| ●「要保存」のレッテルのついた古今の由緒書つきの笑いを、見本でなく手づくの豊富な実例をもとに、徹底して、ことばの問題としてとらえてゆく池内版「笑いの文章読本」。 | |||||||
| J198 画像 |
闇にひとつ炬火あり(ことばの狩人カール・クラウス) | 池内紀 | 筑摩書房 | 1985 初版 |
\700 | 程度A-、帯 | \1,400 |
| ●「ことば遊びから思想が生まれる」…世紀末ウィーンで創刊した個人誌「炬火」に拠って仮借ない筆をふるったクラウス。チェスタトン、魯迅、宮武外骨と比肩されるこの諷刺家・論争家の生涯と“ことばたち”。 | |||||||
| J012 | 天のある人(二十三の物語) | 池内紀 | 河出書房新社 | 1989 初版 |
\600 | 程度A- | \1,600 |
| ●見慣れた、なにげない風景の中から、人間の奥深い世界がほのみえてくる……。「ことばの錬金術師」池内紀、はじめての小説集。書きたかったテーマをひとことにしてしまえば、「町の顔」といったことになる。(本文より) | |||||||
| J013 画像 |
街が消えた! | 池内紀 | 新潮社 | 1992 初版 |
\600 | 程度A- | \1,500 |
| ●四人の建築探偵が東京中をかけめぐる。赤字坂で死んだ身元不明の老人、蒲田のニセ札事件、浅草の縮小された夢ー。次第に街が新たな面影や意外な歴史を見せ始める。多才な著者が巧みに織りなすユニークな連作短篇集。(帯コピーより) | |||||||
| J207 | 錬金術師通り(五つの都市をめぐる短篇集) | 池内紀 | 文藝春秋 | 1993 初版 |
\600 | 程度A-〜B+ | \1,500 |
| ●歴史に翻弄された東欧を舞台に奇妙な物語が始まる。ウィーン、プラティスラヴァ、クラクフ、プラハ、リュブリアーナ。かつて強大なハプスブルク帝国が支配した町々を旅する「私」の前に現れる謎めいた人物たち。 | |||||||
| J200 | 文学探偵帳 | 池内紀 | 平凡社 | 1997 初版 |
\600 | 程度A- | \1,800 |
| ●芥川龍之介の恋歌、樋口一葉の詫び状、夏目漱石の不思議な用語…。わが国の近・現代文学を代表する18人の文学者の生き方、文体、作品を、軽いエッセイスタイルで縦横に論じ、名作の、もうひとつの「真実」を読み解く。 | |||||||
| J209 | モーツァルトの息子(「姿の消し方(改題)」 | 池内紀 | 光文社知恵の森文 | 2008 初版 |
\400 | 程度A- | \720 |
| ●18世紀のウィーンで国中の建物や橋や塔に自分の名前を書きまくった男キュゼラークをはじめ、カフカの恋人、ヒトラーの兄弟、モーツァルトの息子など、実在しながらも歴史からこぼれ落ちた奇人変人30人の数奇な運命を描く。 | |||||||
| J213 | マドンナの引っ越し | 池内紀 | 晶文社 | 2002 初版 |
\600 | 程度A | \1,680 |
| ●無類の旅好きは、気の向くまま世界をめぐる。複数の民族と文化が共存する東欧。土地土地の生活習慣が今も息づくイタリア。温泉と山と漢字の国、台湾。回り道に寄り道ざんまい。しがない酒場へ、理髪店へ、古書店へと足を運ぶ。ある時は、にわか中国語を駆使してマカオの花売りに変身。ヴェネチアではサッカーの勝敗を言い当てる男に会う。バルト海の港町では海難事故で生き残った船長のことを知り…。いずれにしろ何気ない道行きが思い出を作る。ガイドブックには載らない極上の旅22篇。 | |||||||
| J212 | 出ふるさと記 | 池内紀 | 新潮社 | 2008 初版 |
\600 | 程度A、帯 | \1,680 |
| ●漂流、世捨て、雲隠れ。破天荒な人生を歩んだ12人の作家たち(高見順、金子光晴、安部公房、永井荷風、牧野信一、坂口安吾、尾崎翠、中島敦、寺山修司、尾崎放哉、田中小実昌、深沢七郎)。人間存在への愛情と理解に貫かれた列伝紀行。 | |||||||
| J124 | アジア旅人 | 文・金子光晴/写真・横山良 | 情報センター出版局 | 1998 初版 |
\1,200 | 程度A-、函 | \2,940 |
| ●何もかもを清算するために、詩を捨てた詩人金子光晴、一九二八年十一月、長崎から上海行の船に乗る。中国、マレー、ジャワ、スマトラ…五年に及ぶ流浪の旅が始まる。鮮烈の写真と金子光晴アジア紀行の珠玉が織りなす、アジア旅のこころのバイブル。 | |||||||
| J216 | 忘れられた女神たち | 川本三郎 | 筑摩書房 | 1986 初版 |
\600 | 程度A- | \1,600 |
| ●1920年代から50年代にかけて、アメリカを舞台に、華麗に、陽気に、孤独に、そして悲劇的にそれぞれの生を演じ切った魅力的な女たち。銀幕を色どった妖艶な女優、ジャズ・エイジの花形フラッパー、寡作のボヘミアン作家、人種差別と闘い続けた黒人歌手…。アメリカで活躍し、日本ではその存在や生涯があまり知られていない“女神たち”のポートレート集。 | |||||||
| J218 | アカシアの大連 | 清岡卓行 | 講談社文芸文庫 | 2005 19版 |
\500 | 程度A- | \1,260 |
| ●美しい港町、アカシヤ香る大連。そこに生れ育った彼は敗戦とともに故郷を喪失した。心に巣喰う癒し難い欠落感、平穏な日々の只中で埋めることのできない空洞。青春、憂鬱、愛、死。果てない郷愁を篭めて、青春の大連を清冽に描く芥川賞受賞の表題作及び、6編を収録。 | |||||||
| J217 画像 |
弊風一斑 蓄妾の実例 | 黒岩涙香 | 教養文庫 | 1992 初版 |
\800 | 程度A- | \480 |
| ●本書は、明治の異色の日刊紙「万朝報」明治31年7月7日から9月27日まで連載された「弊風一斑 蓄妾の実例」510例を収録したものである。当時、男子の玩弄であった妾に対して、同情を披瀝し、妾を持つ男子に反省を促したものであった。 | |||||||
| J161 | ペヨトル興亡史(ボクが出版をやめたわけ) | 今野裕一 | 冬弓舎 | 2001 初版 |
\800 | 程度A-、帯 | \2,100 |
| ●80〜90年代の文学・アートシーンを駆け抜けた出版社ペヨトル工房。ペヨトル工房は何故解散しまければならなかったのか。主宰・今野裕一と元スタッフが創業から20年を振り返る。 | |||||||
| J159 | 一銭五厘たちの横丁 | 児玉隆也/桑原甲子雄(写真) | 岩波現代文庫 | 2000 初版 |
\500 | 程度A | \1,050 |
| ●一銭五厘のハガキに召集され、横丁の兄ちゃんたちが出征する。ドブ板踏んで、ラッパの響きに送られて…。桑原甲子雄のカメラに収められた留守家族たちの写真を唯一の手がかりに、昭和50年東京下町を児玉隆也はひたすら歩く。天皇から一番遠くに住んだ人たちの戦中戦後の物語。日本エッセイスト・クラブ賞受賞。 | |||||||
| J222 | 昭和夢草紙 | 滝田ゆう | 新潮社 | 1980 3版 |
\500 | 程度A-〜B+、帯 | \1,100 |
| ●少年の頃、夢中で駆けまわった裏町裏通り、横丁や小路。ベーゴマやちゃんばらに明けくれた。しかし、そこは玉の井、大人の町、ちらりちらりと大人の世界がかいま見える。その町も今はなく、ただただ夢、幻として想うばかり…。少年時代に育った懐しい町を絵とエッセイで描き出す。 | |||||||
| J197 | 黒鳥館戦後日記(西荻窪の青春) | 中井英夫 | 立風書房 | 1983 初版 |
\800 | 程度A、函、帯 | \2,300 |
| ●昭和20年代前半から、21年かけてのあの激動の時代の青春日記。ほろ苦く、しかし未来への飛翔を込めた明るさの同居する、若き日の著者を偲ぶ恰好の書。 | |||||||
| J129 | on the border オン・ザ・ボーダー | 中上健次 | トレヴィル | 1986 初版 |
\500 | 程度A- | \1,000 |
| ●漂白の作家が、文学・映画・音楽・写真の境界(ボーダー)をスリリングかつ過激に横断。ジャズ・レゲエ・サムルノリ・坂本龍一を語り、オーストラリア映画・大江健三郎・千年の愉楽を論ずる。ゲストに坂本龍一、村上春樹、栗本慎一郎、ビートたけしを迎えた最新エッセイ&対談集。 | |||||||
| J219 | 東京 都市の明治 | 初田亨 | ちくま学芸文庫 | 1994 初版 |
\500 | 程度A- | \980 |
| ●明治以降、近代化がすすみ中で、都市・東京の街並はどのように変貌していったのか。お雇い外国人やエリートの日本人建築家たちがつくる洋風建築ではなく、江戸以来の伝統的な技術を伝承する棟梁・職人たちと市井の人々のエネルギーがつくりだした「伏流」の建築、あるいは和洋折衷の様式に目を向ける異色の東京論。 | |||||||
| J202 画像 |
幻視者宣言(映画・音楽・文学) | 埴谷雄高 | 三一書房 | 1994 2版 |
\800 | 程度A- | \2,500 |
| ●「死霊」によって戦後文学の極北に佇つ埴谷雄高と政治学者・思想史家として屹立する一代の碩学丸山真男が自在に語り合った偏愛的映画・音楽・文学論。常に時代の先端に身を晒し続けた幻視者による同時代についての証言。 | |||||||
| J182 画像 |
無妙記 | 深沢七郎 | 河出書房新社 | 1975 初版 |
\700 | 程度B+ | \880 |
| ●「無妙記」、「妖術的過去」、「女形」、「因果物語」、「小さなロマンス」、「妖木犬山椒」、「村正の兄弟」、「戯曲 楢山節考」を収録。 | |||||||
| J221 | 東京の印象 | 本間國雄 | 現代教養文庫 | 1992 初版 |
\400 | 程度B+ | \440 |
| ●大正初期の〈東京風景〉を、詩情溢れる百枚のスケッチと百篇の短文とで表す「東京物語」。東京を享楽する画文集。 | |||||||
| J091 画像 |
ウォーク・ドント・ラン | 村上龍/村上春樹 | 講談社 | 1989 15版 |
\2,000 | 程度A-〜B+ | \1,030 |
| ●両村上の対談集。(新人賞の周辺、わが愛する猫たち、チャーリー・パーカーを聴いたか、飢えと文学、作品・表と裏、一人と二人の日常、60年、70年代に何があったか等)。 | |||||||
| J188 画像 |
「父の娘」たち―森茉莉とアナイス・ニン | 矢川澄子 | 新潮社 | 1997 初版 |
\700 | 程度A | \1,600 |
| ●奇しくおなじ生まれの森茉莉とアナイス・ニン。ファーザー・コンプレックスの陽画と陰画である二人を通して「不滅の少女」の原像を探る。 | |||||||
| J138 | 上海シネマと銀座カライライス物語(波瀾万丈、柳田嘉兵衛の八十年) | 山口猛 | 集英社 | 2000 初版 |
\600 | 程度A、帯 | \1,500 |
| ●銀座の片隅に店を構える小さなカレー屋「ニューキャッスル」の柳田嘉兵衛さんは名物オジイちゃん。浅草六区で映写技師として活躍後、中国・上海へ。南京では映画館支配人、戦時中は巡回映写で従軍、そして命からがら引き上げ…。激動の昭和を生き抜いてきた男の涙と笑いと感動の八十年。(帯コピー) | |||||||
| J167 | 詩とダダと私と | 吉行淳之介 | 作品社 | 1997 2版 |
\600 | 程度A-、帯 | \1,500 |
| ●吉行文学の知られざる原点。ダダイストの父=エイスケと私。亡き父の血を確認して、詩を書き始めた淳之介が唯一残した父への思い。エイスケの詩篇31編を併録。 | |||||||
| トップページヘ戻る |