(円、税込)

初版
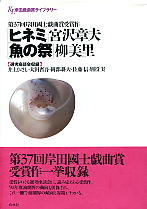
初版

3版

初版
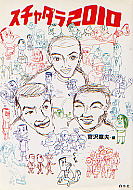
初版

初版
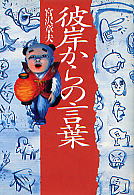
初版

初版

初版

初版
宮沢章夫(遊園地再生事業団)/平田オリザ(青年団)(日本の演劇)−ぱらぶら屋書店目録
| ●トップページ | ●目録の見方 | ●購入方法 | ●Mail | ●当店案内 | ●店主日誌 |
| 程度A: | 若干のヨゴレやキズがあるがそんなに気にならない程度で、新品に近い本及びほとんど新品本 |
| 程度B: | ヤケ・シミ、ヨゴレ等が多少あるぐらいで、古本という感じを与える程度の本 |
| 程度C: | ヤケ・シミ、ヨゴレ等がそれなりにあり、古本らしい古本 |
注)一部抜粋。詳細は上記●目録の見方へ
・本の部位について
天:本の上部
地:本の下部
背:棚に置いた時に見える、タイトルが書いてある部分
小口:背の反対側のページ部分
宮沢章夫・セクション
| 書影 | 番号 | 書名 | 著者・訳者・編者 | 出版社 | 発行版 | 売価 (円、税込) |
状態 | 定価 |
 |
H345 | ヒネミ[新装版] | 宮沢章夫 | 白水社 | 1996 初版 |
\700 | 程度A-〜B+、帯 | \1,900 |
| ●かつて日根水という街があった。北と南に森があった。東西に川が流れていた。主人公ケンジは記憶の片隅を歩きながら、消滅してしまったはずの町の地図を書き続ける……。なつかしさの中へと笑いが微分されてゆく物語。第37回岸田國士戯曲賞受賞作品の改訂新版。書き下ろしエッセイ付き。 | ||||||||
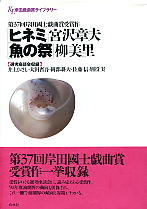 |
H156 | 岸田戯曲賞ライブラリー「ヒネミ」宮沢章夫/「魚の祭」柳美里 | 宮沢章夫/柳美里 | 白水社 | 1993 初版 |
\700 | 程度A-〜B+、帯(少イタミ) | \2,000 |
| ●第37回岸田國士戯曲賞受賞作品、宮沢章夫「ヒネミ」/柳美里「魚の祭」並びに「選考座談会」(井上ひさし、太田省吾、岡部耕大、佐藤信、別役実)を収録。 | ||||||||
 |
H511 | 14歳の国 | 宮沢章夫 | 白水社 | 1999 3版 |
\600 | 程度A-〜B+ | \1,680 |
| ●中学校の午後。そのクラスは体育の時間で教室には誰もいなかった。机、椅子、カバンと、脱いで整えられた制服。教師が5人、姿を見せた―生徒たちの持ち物を検査するために、彼らが生徒のカバンに見つけたのは何だったんだろう?シリアスなのに何故か笑える…。 | ||||||||
 |
H623 | 月の教室 | 宮沢章夫 | 白水社 | 2001 初版 |
\600 | 程度A-〜B+、帯 | \1,890 |
| ●廊下を誰かが走っていく。どこからかピアニカ、聞こえるよ―窓から月が見える午後の教室では、演劇部の女子高生3人が中心に、「ヘビ神社とゆずの木様伝説」と「同級生カップルの揺れる思い出」が描かれていく。台詞の一部や劇中歌を収録したCD付き。 | ||||||||
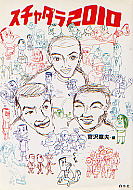 |
H259 | スチャダラ2010 | 宮沢章夫編 | 白水社 | 1996 初版 |
\500 | 程度B+ | \1,200 |
| ●往年の大ヒット曲「今夜はブギー・バック」から物語が始まる会社物の不条理ドラマ集。スチャダラパーが活躍する必笑確実の「超短篇組曲」&「ぼくらがスチャダラ社に入った理由」「雑談レストラン in サウナ」等収録。しりあがり寿の漫画や写真も多数。 | ||||||||
 |
H1265 | 演劇は道具だ | 宮沢章夫 | 理論社 | 2006 初版 |
\500 | 程度A-、帯 | \1,260 |
| ●自己表現が苦手な人は演劇に向いている。不自由な、かたいからだをぐいっと動かしたときに、きしむ音。それこそが表現というものだから-。「演劇」を使って世界や自分やあれこれを考える、シンプルで刺激的な演劇入門。 | ||||||||
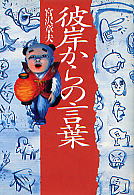 |
H177 | 彼岸からの言葉 | 宮沢章夫 | 角川書店 | 1990 初版 |
\500 | 程度A-〜B+ | \1,200 |
| ●月刊「カドカワ」に3年半にわたって連載されたエッセイ集。「…こうして大人もまた『変なもの、奇妙なもの』が好きだ。好きなくせして、誰もがそれを、大人げないものとして隠そうと努める(中略)その隠された『暗部』を私は『彼岸』と呼びたい気がするのだ。この世界のどこかを『彼岸の地脈』が横たわっている。世界は、この地脈によってつき動かされている(本文より)」 | ||||||||
 |
H085 | 「考える水、その他の石」 | 宮沢章夫 | 同文書院 | 1995 初版 |
\500 | 程度A-〜B+、帯 | \1,600 |
| ●天才バカボンから、現代演劇まで、自由に語り、奔放に論じた思考の冒険!ニュー・クリティカル・エッセイ登場。(帯コピーより) | ||||||||
 |
H1287 | 考える水、その他の石 | 宮沢章夫 | 白水社 | 2006 初版 |
\700 | 程度A-、帯 | \2,100 |
| ●かっこいい笑いとは?マルクス兄弟、赤塚不二夫、タモリ、たけし、竹中直人、いとうせいこう、松本人志、モンティ・パイソン、大人計画…、笑いの「革命児」たちはもちろん、さまざまな表現者の仕事っぷりについて、ときに冷や水を浴びせたり石を投げたりしながらも考えてみた…。1980年代論序説を含む痛快エッセイ。 | ||||||||
 |
H1500 | ユリイカ 臨時増刊 総特集「宮沢章夫」2006年11月号 | 青土社 | 2006 初版 |
\500 | 程度A- | \1,365 | |
| ●「身体と言葉の饗宴としての『鵺/NUE』(対談:宮沢章夫+野村萬斎)」「近過去の世界との対話ー演劇の現在、身体の可能性(対談:宮沢章夫+佐藤信)」「文化的闘争ー80年代地下文化ゲリラはいかに暗躍したか(対談:宮沢章夫+青山真治)」。宮沢章夫自筆年譜+宮沢章夫ビブリオグラフィー他。 | ||||||||
| 書影 | 番号 | 書名 | 著者・訳者・編者 | 出版社 | 発行版 | 売価 (円、税込) |
状態 | 定価 |
 |
H1338 | 東京ノート(平田オリザ1) | 平田オリザ | ハヤカワ演劇文庫 | 2007 初版 |
\400 | 程度B+ | \735 |
| ●美術館の片隅のロビーは、人々が一休みしにやって来ては去る。恋人たち、久しぶりに再会する兄弟と連れ合い、個人所蔵画の寄贈者、学生。会話の断片は世界情勢から個人の悩みまで照らし出す。戦火が広がるヨーロッパから多数の名画が日本に疎開してきているらしい。故郷で老親を世話する長女を理解してくれるのは誰なのか。淡々とした会話から、穏やかな日常とは裏腹の世界を鮮やかに切り取る岸田國士戯曲賞受賞作。 | ||||||||
 |
H1175 | カガクするココロ(ヨムゲキ100) | 平田オリザ | 演劇ぶっく社 | 1999 初版 |
\600 | 程度A-〜B+ | \1,050 |
| ●大学の研究室を舞台にした院生や学生の群像劇。就職や進学、中退、結婚や離婚―。人生の岐路に立たされた若者達が漠然とした不安を抱えたまま、実験やバイトに追われていく日々を描かれる。 | ||||||||
 |
H285 | 平田オリザの仕事1 現代口語演劇のために | 平田オリザ | 晩聲社 | 1996 3版 |
\800 | 程度A-〜B+、帯 | \2,060 |
| ●独自の演劇理論を掲げて意欲的に創作活動を展開してきた著者がまとめた初めての演劇論集。現代演劇界に大きな波紋を投げかけた注目の1冊。 | ||||||||
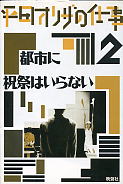 |
H709 | 平田オリザの仕事2 都市に祝祭はいらない | 平田オリザ | 晩聲社 | 1997 初版 |
\800 | 程度A-〜B+ | \2,100 |
| ●混迷する世界と相似形をなすように、芸術は大きな変革の波の中にある。現代演劇の鬼才が、近代演劇の〈到達点〉と現代演劇の〈展望〉を指し示す。 | ||||||||
 |
H1757 | 地図を創る旅(青年団と私の履歴書) | 平田オリザ | 白水社 | 2004 初版 |
\600 | 程度A-〜B+、帯 | \1,890 |
| ●岸田賞受賞作家による待望の自伝エッセイ。平田オリザとその劇団「青年団」が名をなす前の、知られざる青春時代のエピソード紹介も軽快に、現代口語演劇ができあがるまでの日々を活写。 | ||||||||
 |
H261 | 演劇入門 | 平田オリザ | 講談社現代新書 | 2004 13版 |
\300 | 程度A-〜B+ | \693 |
| ●リアルな芝居とは何だろう。戯曲の構造、演技・演出の秘訣とは?平易で刺激的に書かれた演劇入門書。 | ||||||||
 |
H817 | 演技と演出 | 平田オリザ | 講談社現代新書 | 2004 初版 |
\400 | 程度A-〜B+ | \735 |
| ●優秀な俳優の条件とは。演出家はなぜ必要なのか。演劇的な感動をどう起こすか。芝居づくりの基本が誰でもわかる画期的な入門書。 | ||||||||
 |
H506 | 芸術立国論 | 平田オリザ | 集英社新書 | 2005 2版 |
\400 | 程度A-〜B+ | \693 |
| ●日本再生の鍵は、芸術文化による立国にある。芸術文化行政について、その精神、経済、教育等の面から芸術の必要性と、実効性ある芸術文化政策を提言するヴィジョンの書。 | ||||||||
 |
H1774 | 対話のレッスン | 平田オリザ | 講談社学術文庫 | 2015 初版 |
\400 | 程度A- | \972 |
| ●日常会話」や「雑談」は得意でも「対話」は苦手なことが多い日本人。ふだん同じ価値観の仲間とばかり会っているので、異なるコンテクストの相手と議論をしなくて済んでしまう。文化の違う相手と交渉したり共同作業をする経験が、まだ日本人には少ないのだ。さらに携帯電話などの登場で、世代間のギャップが広がる。それではどのようなスキルが必要なのか。豊富な具体例をもとに、新しいコミュニケーションの在り方を真摯に探る。 | ||||||||
 |
H1435 | 「リアル」だけが生き延びる(012 That's Japan) | 平田オリザ | ウエイツ | 2003 初版 |
\400 | 程度A- | \788 |
| ●大きく様変わりする日本社会に必要な、「リアル」な生き方とはどういうものか。常に新しい風を送りつづける演劇界の革命児が、劇空間を超えて熱く語る。 | ||||||||
 |
H1176 | 受験の国のオリザ | 平田オリザ | 晩聲社 | 1985 2版 |
\700 | 程度B+ | \1,300 |
| ●偏差値が、予備校生の存在地点を示す座標軸なら、いま僕は…。問いつつ、迷いつつ、朗らかに書き下ろした受験生の青春讃歌。 | ||||||||
 |
H1559 | 十六歳のオリザの冒険をしるす本 | 平田オリザ | 講談社文庫 | 2010 初版 |
\400 | 程度A-、帯 | \780 |
| ●世界一周自転車旅行を計画した少年オリザは、1979年5月、いよいよ二年間の休学届を高校に提出し、世界へ向かって旅立った。親子関係、友情、異性、民族、貧困、人生、芸術…さまざまな問題にぶつかり、時に悩みながら記録した、劇作家・平田オリザの処女作にして、色褪せることのない傑作冒険旅行記。 | ||||||||
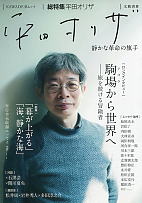 |
H1775 | 文藝別冊 総特集 平田オリザ(静かな革命の旗手) | 河出書房新社 | 2015 初版 |
\500 | 程度A- | \1,404 | |
| ●【平田オリザ ロングインタビュー】「駒場(アゴラ)から世界へ――旅を続ける冒険者」。【戯曲】舞台版「幕が上がる」/オペラ「海、静かな海」。【平田オリザコレクション】イノベーションに関する文人的考察一劇作家から見た日本語教育の課題と展望ソウイウモノヲ、ワタシハ、ミタイ。【対談・座談会】石黒浩×平田オリザ /関川夏央×平田オリザ。【エッセイ】飴屋法水、岩松了、岡田利規他。【論考】河合祥一郎、川本三郎他。 | ||||||||
| トップページへ戻る |