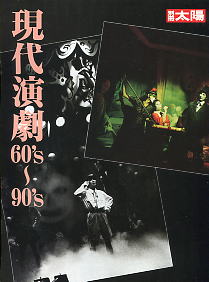
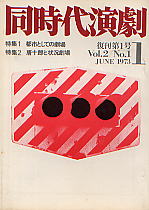

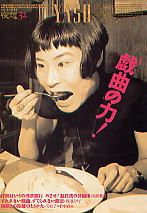


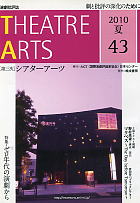
H1628
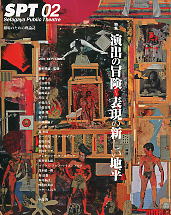


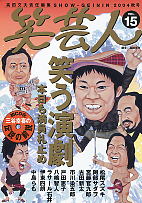


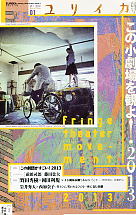
「せりふの時代」「シアターアーツ」「PTパブリックシアター」「演劇人」「しんげき」「PT]他演劇雑誌と演劇特集の雑誌及び公演プログラム-ぱらぶら屋書店目録
| ●トップページ | ●目録の見方 | ●購入方法 | ●Mail | ●当店案内 | ●店主日誌 |
| 程度A: | 若干のヨゴレやキズがあるがそんなに気にならない程度で、新品に近い本及びほとんど新品本 |
| 程度B: | ヤケ・シミ、ヨゴレ等が多少あるぐらいで、古本という感じを与える程度の本 |
| 程度C: | ヤケ・シミ、ヨゴレ等がそれなりにあり、古本らしい古本 |
注)一部抜粋。詳細は上記●目録の見方へ
・本の部位について
天:本の上部
地:本の下部
背:棚に置いた時に見える、タイトルが書いてある部分
小口:背の反対側のページ部分
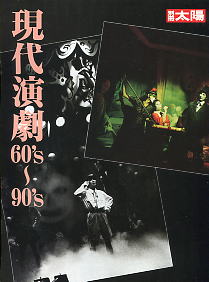 |
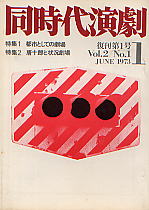 |
 |
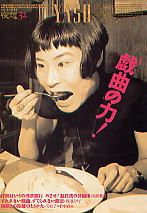 |
 |
 |
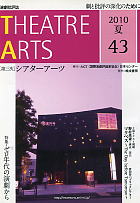 |
| H498 | H968 | H106 | H1456 | H607 | H1039 |
H1628 |
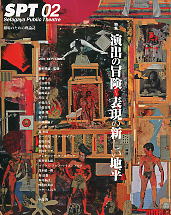 |
 |
 |
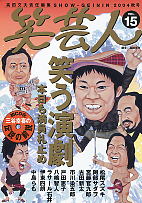 |
 |
 |
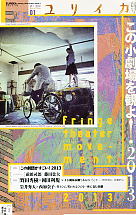 |
| H1440 | H1324 | H1118 | H672 | H1355 | H1420 | H1508 |
| 番 | 書名 | 著者・編者 | 出版社 | 発行版 | 売価(円、税込) | 状態 | 定価 |
| H498 画像 |
別冊太陽 現代演劇60’~90’ | 平凡社 | 1991 初版 |
\1,300 | 程度A-~B+ | \2,500 | |
| ●60年代後半から90年までに活躍したいわゆる“小劇場”と呼ばれる演劇集団と個人の計65と舞踏集団と個人計7を紹介。その他、唐十郎、野田秀樹等の劇作家等18人の寄稿エッセイ、演劇史年表等を所収。 | |||||||
| H968 画像 |
雑誌「同時代演劇」(復刊第1号Vol.2/No.1 JUNE1973) | 株式会社ル・マルス | 1973 初版 |
\800 | 程度B+ | \520 | |
| ●特集1【都市としての劇場】「劇場を盗む(津野海太郎)」「解放された劇場ーオデオン座で何が起ったのか(利光哲夫)」「泥棒・乞食・役者の宿(シェークスピアの劇場(海野弘)」「祭師たちの都市戦略ー劇場街<渋谷>批判(グループ雛芥子)」「最後の火事ー劇場論ノート(佐藤信)」他。特集2【唐十郎と状況劇場】「対談/実在としての虚構(寺山修司+鈴木忠志)」「日本人を殺せ(唐十郎)」「針のない時計の世界ー唐十郎の初期作品をめぐって(大笹吉雄)」他。 | |||||||
| H1456 画像 |
雑誌「夜想」32(特集戯曲の力) | ペヨトル工房 | 1993 初版 |
\600 | 程度A-~B+ | \1,300 | |
| ●「劇作の視点(天野天街、岩松了、加納幸和、ケラ、高泉淳子、高見亮子、鄭義信、天光真弓、林巻子、平田オリザ、三谷幸喜、宮沢章夫、柳美里、横内謙介、渡辺えり子)」。インタビュー「めざせ!超自我の共同体(島田雅彦)」「廃れない戯曲、棄てられない劇団(渡辺えり子)」「演劇との距離のとりかた(岩松了×竹中直人)」「書く職人でありたい(三谷幸喜)」他。エッセイ「浅草旅行(片桐はいり)」他。 | |||||||
| H106 画像 |
雑誌「WAVE」10(特集都市と演劇) | ペヨトル工房 | 1986 初版 |
\600 | 程度A-~B+ | \980 | |
| ●「生きている廃墟(石橋蓮司)」「MICHIYUKI地球に残った僕達(撮影荒木経惟)」「チキューニノコッタボクタチ(嶋田久作VS片桐はいり)「新しいアジア的グループの発生(石井總互VS大須賀勇)」「エフェメラの都市に立つ(川村毅)」他。 | |||||||
| H1508 画像 |
雑誌「ユリイカ」2013年1月号特集「この小劇場を観よ!2013」 | 青土社 | 2013 初版 |
\500 | 程度A- | \1,300 | |
| ●演劇は社会のさまざまな問題を表象する以前に、ひとつの最小単位の社会であり、言うなればひとつの舞台を作りあげる過程は社会を編み直すための格好のレッスンである。利賀や静岡に加えていわき、富士見、横浜、山口、北九州、熊本…とひとの移動を伴っていよいよ活性化する地方の小劇場の現状も見据えつつ、おそらくは演劇にとどまらない新たな文化的パラダイムの布置に目をこらしたい。【資料】この劇団がすごい! 2013(編=小澤英実) | |||||||
| H607 画像 |
季刊「せりふの時代」VOL.32(2004年夏) | 小学館 | 2004 初版 |
\800 | 程度A-~B+ | \900 | |
| ●特集『世界に向けて発信!』―「ニューヨークで平成中村座の夢を(中村勘九郎インタビュー)」「異文化交流という幸福(野田秀樹インタビュー)」「海外での日本の演劇(伊達なつめ)」他、戯曲「アオイバラ(渡辺えり子)」、「渚家にて(大橋泰彦)」、「もやしの唄(小川美玲)」、「留守太平間(莊梅岩)」等。 | |||||||
| H1355 画像 |
季刊「せりふの時代」VOL.38(2006年冬) | 小学館 | 2006 初版 |
\800 | 程度A-~B+ | \1,000 | |
| ●特集『これからの演劇と教育』「対談/岸田今日子VS別役実」「インタビュー/鴻上尚史」「インタビュー/横内謙介」。戯曲―北村想「もろびとこぞりてVer.2,3」、川村毅「フクロウの賭け―神なき国の夜2」、渡辺えり子「風回廊(後編)」、本谷有希子「乱暴と待機」の四作品。他。 | |||||||
| H1621 | 季刊「せりふの時代」VOL.39(2006年春) | 小学館 | 2006 初版 |
\900 | 程度A-~B+ | \1,000 | |
| ●特集『新劇の底力』「対談/〈文学座〉坂口芳貞VS青木豪」「インタビュー/〈民藝〉梅野泰靖/〈円〉橋爪功/〈俳優座〉田中壮太郎/〈青年座〉魏涼子/〈昴〉河田園子」「寄稿/扇田昭彦」「戯曲―岩松了「マテリアル・ママ」、長塚圭史「桜飛沫」、ごまのはえ「ヒラカタ・ノート」の三作品。他。 | |||||||
| H945 | しんげき1991年6月号NO.460 | 白水社 | 1991 初版 |
\400 | 程度B+ | \680 | |
| ●シリーズ長編評論/北村想「帰郷論ー喪失の風景」。戯曲/山崎哲「骨の鳴るお空ー連続幼女誘拐事件」、別役実「魔女ものがたり その2ー寝られます」。WORK SONG PLAY SONGーイッセイ尾形、他。 | |||||||
| H1039 画像 |
雑誌「シアターアーツ」16(2002年1号)特集演劇と笑い(その過去・現在・未来) | 晩成書房 | 2002 初版 |
\600 | 程度A-~B+ | \1,680 | |
| ●「基調(瀬戸宏)」「共同討論/演劇と笑いー研究と立場から(市川明、大笹吉雄、永田清他)」「共同討論/演劇と笑いー演劇創造の立場から(岩崎正浩、土田英生、松田正隆他)」「笑いの最前線ー井上ひさし/野田秀樹/つかこうへい/劇団☆新感線/演劇弁当猫ニャー/女性劇作家の生み出す笑い/ダンスで笑う(関西のダンサーを中心に)」他。 | |||||||
| H1439 | 雑誌「シアターアーツ」18(2003年1号)特集演劇批評の現在 | 晩成書房 | 2003 初版 |
\600 | 程度A-~B+ | \1,680 | |
| ●「共同討議:現代日本演劇批評はどうあるべきか?(古後奈緒子/瀬戸宏/外岡尚美/貫成人/日比野啓/森山直人)」「論考:野田学/太田耕人/新野守弘/副島博彦/西堂行人」。「海外演劇人インタビュー:サイモン・マクハーニー」。「AICT会員アンケート/演劇批評を考える上でもっとも重要な批評書・論文は」他。 | |||||||
| H1489 | 雑誌「第二次シアターアーツ」26(2006年春号) | 晩成書房 | 2006 初版 |
\500 | 程度A- | \1,050 | |
| ●「2005年を振り返る―ベスト舞台/ベスト・アーティスト発表」「『歌わせたい男たち』永井愛インタビュー」「第10回シアターアーツ賞発表」「アングラの源流を探る6-蜷川幸雄」他。 | |||||||
| H1863 | 雑志「第二次シアターアーツ」29(2006年冬号) | 晩成書房 | 2006 初版 |
\500 | 程度A- | \1,050 | |
| ●小特集①「ブレヒトVSブレヒト」、小特集②「東京VSベルリン」、報告「AICソウル大会」、上演テクスト「マレビトの会『アウトダフェ』作・演出 松田正隆」他。 | |||||||
| H1149 | 雑誌「第二次シアターアーツ」35(2008年夏号) | 晩成書房 | 2008 初版 |
\500 | 程度A- | \1,050 | |
| ●「共同討議/演劇はこうして20世紀を越えた(坂手洋二/扇田昭彦/西堂行人/新野守広/高橋宏幸)」、「インタビュー/ヨシ笈田(俳優・演出家)、シュテファン・ケーキ(『ムネモパーク』演出家)」、「パフォーマンスの美学(エリカ・フィッシャー=リヒテ)」、「上演記録/Port Bツアー・パフォーマンス サンシャイン62/解説鴻英良:歴史と地理を召還するパフォーマティブの試み」他。 | |||||||
| H1734 | 雑誌「第二次シアターアーツ」39(2009年夏号) | 晩成書房 | 2009 初版 |
\500 | 程度A- | \1,050 | |
| ●ヤン・ファーブル上演テキスト「寛容のオルギア」、[インタビュー]ヤン・ファーブル/佐藤信、[座談会]身体表現の社会性/高嶺格/手塚夏子/山下残/古後奈緒子/武藤大祐、その他執筆者/西堂行人/副島博彦/野田学/高橋宏明/山口宏子/谷岡健彦/江森盛夫/河野孝。 | |||||||
| H1856 | 雑誌「第二次シアターアーツ」42(2010年春号) | 晩成書房 | 2010 初版 |
\500 | 程度A~B+ | \1,050 | |
| ●2009年間回顧[座談会]/扇田昭彦/西堂行人/江森盛夫/高萩宏/高橋宏幸。「ダンス年間回顧(木村覚)」、「関西演劇年間回顧(今村修)」。[上演ドキュメント]リミニ・プロトコル『Cargo Tokyo-Yokohama』。[インタビュー]イェルク・カレンバウアー(Cargo演出家)」。その他の執筆者/喜志哲雄/田野倉稔/山口宏子/谷岡健彦/河野孝。 | |||||||
| H1628 画像 |
雑誌「第三次シアターアーツ」43(2010年夏号) | 晩成書房 | 2010 初版 |
\600 | 程度A- | \1,296 | |
| ●特集=ゼロ年代の演劇から/巻頭対談「ニッポンの演劇(佐々木敦×西堂行人」/座談会「ゼロ年代の演劇から(扇田昭彦×野田学)×梅宮いつき×西堂行人)」/「アンケートー国際演劇評論家協会会員に聞く2000年代のベスト舞台、2000年代ベストテン、2000年代演劇年表(2000~2009)」。上演テクスト「野村萬斎構成・演出(世田谷パブリックシアター)『マクベス~The Day before Tomorrow~』」他。 | |||||||
| H1629 | 雑誌「第三次シアターアーツ」45(2010年冬号) | 晩成書房 | 2010 初版 |
\600 | 程度A- | \1,296 | |
| ●特集=世界演劇のただ中へ/対談「80年代のラディカリズムー『新宿八犬伝』全5巻完結(川村毅×西堂行人)」/座談会「ポストドラマ演劇をめぐって(平田栄一朗×岡本章×新野守広)」。上演テクスト「前川知大・作 イキウエ『図書館的人生Vol.3 食べものの連鎖』」/「長田育恵・作 演劇ユニットてがみ座『乱歩の恋文』」。他。 | |||||||
| H617 | 雑誌「テアトロ」2004年9月号 | カモミール社 | 2004 初版 |
\500 | 程度A-~B+ | \1,200 | |
| ●特集『宮本研と戦争の劇』―扇田昭彦/江原吉博/岩波剛。劇界56人によるエッセイ特集「わたしの好きな劇場・好きな芝居」。戯曲「心中天の綱島(原作・近松門左衛門/脚本・山元清多)」他。 | |||||||
| H685 | 雑誌「テアトロ」2004年12月号(通巻757号) | カモミール社 | 2004 初版 |
\500 | 程度A-~B+ | \1,260 | |
| ●特集『演劇事件簿2004』―小松幹夫/田中聡/九鬼葉子/村井健/赤坂治績/中本信幸/みなもとごろう/麻生直。戯曲『松陰狂死曲(黒川欣映)』『賢治幻想 電信柱の歌(別役実)』。批評的エッセイ「とやま舞台芸術祭利賀2004秋演劇公演から(矢沢英一)」他。 | |||||||
| H730 | 雑誌「悲喜劇」 特集・演劇の大衆性をさぐる1996年8月(NO.550) | 早川書房 | 1996 初版 |
\400 | 程度A-~B+ | \900 | |
| ●特集・演劇の大衆性をさぐる「50年“女の一生”とともに(戍井一郎)」「『アンネの日記』の40年(渾大防一枝)」「「『森は生きている』大衆性と芸術性(八橋卓)」他。戯曲「イリーナ さあ おきて」(村井志摩子)、戯曲「クラムボンは笑った」(別役実)。 | |||||||
| H1660 | 雑誌「悲劇喜劇」特集・動物と演劇人2013年6月(NO.752) | 早川書房 | 2013 初版 |
\400 | 程度A-~B+(裏表紙折れ痕・修復済) | \1,300 | |
| ●特集:動物と演劇人、執筆者は別役実、川村毅、ケラリーノ・サンドロヴィッチ、横内謙介、東憲司、戍井昭人、加藤武他。収録戯曲「不条理・四谷怪談(別役実)」「あかいくらやみ(長塚圭史)」。 | |||||||
| H1603 | 雑誌「悲劇喜劇」特集・第3回ハヤカワ『悲劇喜劇』賞2016年5月(NO.780) | 早川書房 | 2016 初版 |
\500 | 程度A- | \1,445 | |
| ●特集=第三回ハヤカワ『悲劇喜劇』賞。第三回ハヤカワ『悲劇喜劇』賞選考会/小藤田千栄子 高橋豊 鹿島茂 辻原登 今村忠純。『リチャード二世』──ネクスト・シアターとゴールド・シアターの豪華な共演/小藤田千栄子。傑作との遭遇・未遭遇/鹿島茂事。ハヤカワ『悲劇喜劇』賞選評/辻原登。劇の力は、世界を変える/今村忠。純魅惑的な蜷川シェイクスピア劇『リチャード二世』/高橋豊。蜷川シェイクスピアという洗礼/内田健司。気高き反逆者、公爵夫人を生きて/重本惠津子。常に新しさを探し求める蜷川演出の魅力/井上尊晶。戯曲:8月の家族たち トレイシー・レッツ=作/目黒 条=翻訳/ケラリーノ・サンドロヴィッチ=上演台本。他。 | |||||||
| H1604 | 雑誌「悲劇喜劇」特集・東の演劇/西の演劇2016年7月(NO.781) | 早川書房 | 2016 初版 |
\500 | 程度A- | \1,445 | |
| ●特集=東の演劇 西の演劇。東の演劇 西の演劇 矢野誠一。浅草軽演劇は、最高級の学校だった/萩本欽一。わたしの浅草/戌井昭人。地域から東京へ/ 西川信廣。東の演劇を求めて/佐藤信。“拠点"が関西学生演劇ブームを生み出した/いのうえひでのり。関西学生演劇ブームのはじまり─劇団そとばこまちの時代/辰巳琢郎。オレンジの中島さんのこと/マキノノゾミ。マイナーな記憶のほうへ/松田正隆。私の大阪/内藤裕敬。東京の小劇場は実験的であり続けているのか?/西堂行人。森繁久彌の大阪と三木のり平の東京/横澤祐一。関西小劇場はコミュニケーションの中心地/九鬼葉子。戯曲;あわれ彼女は娼婦 ジョン・フォード=作 小田島雄志=翻訳、埒もなく汚れなく 瀬戸山美咲=作 。他。 | |||||||
| H1728 | 雑誌「悲劇喜劇」特集・追悼「蜷川幸雄」2016年9月(NO.782) | 早川書房 | 2016 初版 |
\500 | 程度A-(少しなり) | \1,500 | |
| ●追悼・蜷川幸雄(カズオ・イシグロ/トム・ストッパード/岩松了/ケラリーノ・サンドロヴィッチ/ノゾエ征爾他)、収録戯曲「ビニールの城(唐十郎)」「遊侠・沓掛時次郎(北村想)」他。 | |||||||
| H1257 | 雑誌「PTex2」 パブリックシアター・エクストラ「特集伝統と現代をつなぐもの」 | 世田谷パブリックシアター | 2002 初版 |
\400 | 程度A-~B+ | \800 | |
| ●特集・伝統と現代をつなぐもの(野村万作/野田秀樹/川村毅/高橋悠治/渡邊守章/三浦雅士/堂本正樹/西堂正人/可合祥一郎/ヨシ笈田)」「座談会:『出発点に回帰する』野村萬斎/いとうせいこう/伊藤キム/松井憲太郎」「特別寄稿:目の演劇と耳の演劇ーケベックのシェイクスピア(R・ルハージュ)」「戯曲『まちがいの狂言』グローバル・バージョン(作/W・シェイクスピア、脚本/高橋康也)」。 | |||||||
| H814 | 雑誌「PTex2」 パブリックシアター・エクストラ2「特集古典からの発想」 | 世田谷パブリックシアター | 2003 初版 |
\400 | 程度A-~B+ | \1,000 | |
| ●特集・古典からの発想「古典からの発想(対談松岡正剛/野村萬斎)」「『古典と現代』についての雑感(川村毅)」「『能』からの発想(鐘下辰男/聞き手・松井憲太郎)」「現代能楽へ(笠井叡)」「換喩の狂言(いとうせいこう)」「古典としての身体(野田学)」他。 | |||||||
| H1324 画像 |
SPT1(特集戯曲―ことばの持っている力) | 野村萬斎監修 | 世田谷パブリックシアター(発行)/工作舎(発売) | 2004 初版 |
\500 | 程度A- | \1,000 |
| ●特集「特集戯曲―ことばの持っている力」。執筆者は、江戸馨/大竹伸朗/岡崎武志/奥泉光/鐘下辰男/鎌田東二/鴨下信一/川崎徹/川田順三/川村毅/国本武春/小森陽一/外岡秀俊/土屋恵一郎/筒井康隆/永井愛/野村萬斎/藤野千春/松井憲太郎/松尾スズキ/宮沢章夫。 | |||||||
| H1440 画像 |
SPT2(特集演出の冒険―表現の新しい地平) | 世田谷パブリックシアター(発行)/工作舎(発売) | 2005 初版 |
\500 | 程度A- | \1,000 | |
| ●特集「特集演出の冒険―表現の新しい地平」。執筆者は、野村萬斎/太田省吾/大竹伸朗/長塚圭史/堤幸彦/ラサール石井/坂手洋二/茂木健一郎/平田オリザ/小池昌代/四方田晴彦/伊藤キム/森達也/斎藤環/ジョセフ・ナジ/川俣正/トーマス・オスターマイヤー/マリウス・フォン・マイエンブルク/フレデリック・フィスバック他。 | |||||||
| H1441 | SPT3(特集レパートリー―記憶の継承と更新) | 世田谷パブリックシアター(発行)/工作舎(発売) | 2006 初版 |
\500 | 程度A- | \1,000 | |
| ●特集「レパートリ―記憶の継承と更新」。執筆者は、野村萬斎/松井憲太郎/小林康夫/小池博史/滝千尋/ベータ―・ゲスナー/栗山民也/宮沢章夫/坂手洋二/鐘下辰男/扇田昭彦/天児牛大/結城孫三郎/エリック・ヴィリニ/石井達朗他。 | |||||||
| H1325 | SPT4(特集:演技しているのは誰か?) | 野村萬斎監修 | 世田谷パブリックシアター(発行)/工作舎(発売) | 2007 初版 |
\500 | 程度A- | \1,000 |
| ●特集「演技をしているのは誰か?」。執筆者(インタビュー相手)は、飯沢耕太郎/大竹伸朗/岡崎武志/岡田利規/白井晃/田中泯/谷川多佳子/豊竹咲甫大夫/長嶋有/野村萬斎/平田オリザ/弘中惇一郎/松井憲太郎/松本修/宮台真司/渡邊守章。 | |||||||
| H1759 | SPT10(終号)」(特集劇場技術の世界ー“創造する劇場”の舞台裏) | 世田谷パブリックシアター(発行)/工作舎(発売) | 2014 初版 |
\500 | 程度A-~B+ | \1,000 | |
| ●特集「劇場技術の世界-“創造する劇場”の舞台裏」、監修・野村萬斎。インタビューが中心で、主な被インタビュー者/野村萬斎/熊谷明人/福田純平/柘植幸久/尾崎弘征/勝康隆/水森利明/中野かおる。上演台本/『花子』「班女』(現代能楽集Ⅶ『花子について』より)作・倉持裕。 | |||||||
| H1087 | 演劇人(新しい演劇人のための季刊誌)2000年Jan.NO.4 | (財)舞台芸術財団演劇人会議 | 2000 初版 |
\500 | 程度A-~B+ | \1,050 | |
| ●特集「世界の中の日本演劇」。巻頭座談会「外国演劇の変容と影響」(戌井市郎/倉林誠一郎/森秀男)。「日本演劇史における外部の発見ー『小山内薫とスタニスラフスキとの出会い(貝澤哉)』『ドイツ前衛演劇と日本演劇の出会い=築地小劇場の位相(谷川道子)』『日本演劇における異国との遭遇=フランスの場合(佐伯隆幸)』『シェイクスピアと日本演劇の出会い(可谷祥一郎)』」。他。 | |||||||
| H479 | 演劇人(新しい演劇人のための季刊誌)2000年Jul.NO.5 | (財)舞台芸術財団演劇人会議 | 2000 初版 |
\500 | 程度A-~B+ | \1,000 | |
| ●特集21世紀の演劇とその環境。巻頭座談会「21世紀の演劇ー表現・批評・環境ー(山口昌男、渡辺保、鈴木忠志)」、「身体技法の21世紀(対談:佐々木正人・平田オリザ)」、「サバイバルの時代の劇団、そして劇場(衛紀生)」、「ピッコロ劇団と日本の劇場芸術の過去・現在(インタビュー:山根淑子)」、「日本の演劇環境を問う(シンポジウム)」他。 | |||||||
| H1472 | 演劇人(新しい演劇人のための季刊誌)2004年 NO.16 | (財)舞台芸術財団演劇人会議 | 2004 初版 |
\500 | 程度A-~B+ | \1,050 | |
| ●利賀フェスティバル〈2004〉よりシンポジウム「地方分権と日本文化の将来(公共ホールと指定管理者制度をめぐって)」伊藤裕夫・鈴木滉二郎・野田邦弘・鈴木忠志、「芸術創造・文化形成と行政運営の変化(鈴木滉二郎)」「個性的な空間が提示するもの(志賀亮史)」他。「新連載共同討議≪近代日本の演劇≫第1回分裂する近代・複数のナショナリズム(石原千秋・兵藤裕己・渡辺保・菅孝行)」、「反復される模倣・忘却(菅孝行)」「明治期の演劇改良について(石澤秀二)」他。 | |||||||
| H1326 | 演劇人(新しい演劇人のための季刊誌)2009年 NO.25(終刊号) | (財)舞台芸術財団演劇人会議 | 2009 初版 |
\500 | 程度A-~B+ | \1,050 | |
| ●1.対話:いま<芸術・文化活動に問われていること>『<精神の型>としての専門家ー集団の目的とリーダーの役割』(鈴木忠志+金森穣)、2.<有度サロン>公演/鈴木忠志演出『ディオニュソス』アクター・トークより『<集団>というフィクションの力』(鈴木忠志氏に聴く)、3.座談会=地域における<芸術・文化活動>の課題と展望『考える<人と場>のネットワークの形成へ』(下山久+石川利江+中島諒人+斉藤郁子/司会管孝行)他。 | |||||||
| H1420 画像 |
舞台芸術01(特集グローバリゼーション) | 京都造形芸術大学センター舞台芸術研究センター | 月曜社 | 2002 初版 |
\700 | 程度A-~B+(帯がかかならない部分の背、少色落ち)、帯 | \2,100 |
| ●責任編集:太田省吾/鴻英良。執筆者:ニーラム・チャウドゥリー/西谷修/?秀美/内野儀/プトゥ・ウィジャヤ/エリカ・マンク/熊倉敬聡/海上宏美/ピーター・エカソール/究極Q太郎他。連載:観世榮夫/フレデリック・ジェイムソン/川村毅他。戯曲「キッチン・カタ(スルジット・パーター)」。 | |||||||
| H1787 | 舞台芸術22(特集〈劇場〉の現在形―「拡張」と「拡散」の間で) | 企画・編集:京都造形芸術大学センター舞台芸術研究センター | 発行:角川文化振興財団/発売:株式会社KADOKAWA | 2019 初版 |
\700 | 程度A | \1,650 |
| ●特集「〈劇場〉の現在形―「拡張」と「拡散」の間で」に対して3つの視点から渡邊守章、きたまり、宮沢章夫、黒瀬陽平、蔭山陽太、三浦基らが発言。他にアジアにおける演劇教育(平井愛子)をはじめ論考多数を収載。 | |||||||
| H1846 | 雑誌「a+a(美学研究)」12 特集「シアトロクラシー(観客の美学と政治学)」 | 大阪大学美学研究室 | 松本工房 | 2018 初版 |
\600 | 程度A-~B+、帯 | \1,620 |
| ●執筆は、田中均/クリストフ・メンケ/梶原将志/海老名剛/柿木伸之/石田圭子/井上由里子/土田耕督/河口篤/高安啓介/山下泰平春。 | |||||||
| H1849 | 文学ムック 「ことばと」vol.2 特集「ことばと演劇」 | 書肆侃侃房 | 2020 初版 |
\600 | 程度A- | \1,870 | |
| ●[戯曲]「スワン666(飴屋法水)」「THE VACUUM CLEANER(岡田利規)」。[対談]山下澄人×佐々木敦「演劇の生成、小説の誕生」。[小説]「唯一無二(綾門優季)」「住吉コーポ二〇一(犬飼勝哉)」「どこ行った(鳥山フキ)」「はなのゆくえ(中村大地)」「イヌに捧ぐ(松原俊太郎)」「蟹いいよ(宮崎玲奈)」「植物の家(本橋龍)」。他。 | |||||||
| H1501 | 別冊プラスアクト Vol.3「ニッポンの演劇」 | ワニブックス | 2010 初版 |
\400 | 程度A- | \990 | |
| ●巻頭特集「NODA・MAP最新作の魅力に迫る!野田秀樹という『ザ・キャラアクター』“ニッポンの演劇”の代名詞的存在、野田秀樹の魅力を徹底考察―野田秀樹・宮沢りえ・古田新太・藤井孝・美波・池内博之・チョウソンハ・田中哲司・銀粉蝶・橋爪功・スタッフインタビュー、野田秀樹の作品解説アーカイブ」。第2特集「ゼロから学ぶ、30年史 入門、劇団☆新感線」。第3特集「演劇シーンの現在を知る、インタビュー&ルポ企画、長塚圭史インタビュー」他。 | |||||||
| H1118 画像 |
雑誌「JAMCI」(1996年12月号VOL.26) | じゃむち通信 | 1996 初版 |
\500 | 程度A-~B+ | \500 | |
| ●「FRONT INNTERVIEW―高泉淳子」「STAGE―黒テント『KAN-GAN』、東京壱組『果てるまで行く』、惑星ピスタチオ『Believe』」「FEATURE ARTICLE―特集/宮澤賢治 再構築されるその宇宙―インタビュー:北村想/平田オリザ、京都と岩手をつなぐ地下水脈:松田正隆/鈴江俊郎/右来左往/キタモトマサヤ、対談:『イーハトーボの音楽劇/銀河鉄道の夜』白井晃×能祖政夫。他 | |||||||
| H656 | 雑誌「國文學」(1998年3月号)演劇ーパフォーミング・アーツとして | 學燈社 | 1998 初版 |
\500 | 程度A-~B+ | \1,050 | |
| ●<現代演劇は何を得たか>―「兎からゴドーへ(別役実)」「『静かな劇』にみる世紀末の演劇(七字英輔)」「シェイクスピアの再解釈(松岡和子)」他。<作劇術の今後>―「現代演劇と演技論(扇田昭彦)」「テクノロジー/身体/演劇(西堂行人)」他。<交錯する芸態>、<アート・マネージメントの問題>、<バレエ・ダンス・ミュージカル・オペラ>、<ニュー・ウェーブ=異能の劇作家論>―野田秀樹他12名。計188頁中137頁の特集。 | |||||||
| H1552 | 雑誌「國文學」(2005年11月号)演劇ー国家と演劇 | 學燈社 | 2005 初版 |
\500 | 程度A-~B+ | \1,300 | |
| ●「国家と演劇(大笹吉雄)」「シェイクスピア劇の最前線(河合祥一郎)」「チェーホフ劇の最前線〈村井健)」「ベケットは必要か?(内野儀)」「ベルリンの演劇(新野守広)」「二十一世紀の劇作家たち―長塚圭史、三浦大輔、そして岡田利規(七字英輔)」「[対談]演劇の日常と異空間(坂手洋二/長塚圭史)」。「レパートリー・システムとは何か」「新国立劇場はどこへ行くか」「俳優養成の現在」他。 | |||||||
| H672 画像 |
笑芸人VOL.15笑う演劇 本日も満員札止め | 高田文夫責任編集 | 白夜書房 | 2004 初版 |
\900 | 程度A-、付録CD(「笑う演劇」特選音源、但し開封済み) | \2,500 |
| ●「大人計画」と「劇団☆新感線」という二大人気劇団の他、注目の劇団や役者を大フィーチャー。その魅力を「笑劇人」的視点、“笑い”にスポットをあてながら縦横無尽に紹介。松尾スズキ、阿部サダヲ、宮藤官九郎、古田新太、市川染五郎、戸田恵子、八嶋智人、ラサール石井、伊東四朗、中島らも他。 | |||||||
| H1535 | 雑誌「東京人」(1989年12月号NO.18)特集・劇場が都市の街並みを変える | 都市出版 | 1989 初版 |
\400 | 程度A-~B+(最終頁に1ヵ所蔵書印あり) | \980 | |
| ●座談会「始めに芝居小屋ありき(岡副昭吾/田村晴也/堤清二/山崎正和)」、インタビュー「つかこうへい/東京の演劇状況を語る」、大笹吉雄「大一座の座長たち」、西堂行人「いま、都市のなかで新しい芝居が生まれる場所」、八木忠栄「国際演劇祭の拠点になった暗がりの街池袋」、岡村直樹「三軒茶屋再開発で世田谷区に文化中心が生まれる」、内田洋一「若者の街渋谷は“文化村”の出現でどこまで変わるか」他。 | |||||||
| H1594 | 東京国際演劇祭’92 公式プログラム | 東京国際演劇祭実行委員会 | 1992 初版 |
\400 | 程度A-~B+ | \950 | |
| ●1992年に開催された「東京国際演劇祭」の公式プログラム。 | |||||||
| H1788 | フェスティバル/トーキョー9 ドキュメント | フェスティバル/トーキョー実行委員会 | フェスティバル/トーキョー | 2010 初版 |
\1,000 | 程度A- | \2,500 |
| ●春/秋92日間の全ドキュメント。豪華批評家から寄せられた各作品やフェスティバルを読み解くためのテキストに加え、アーティストやディレクターによる座談会やフォトギャラリー、F/T09の実績データなど充実のコンテンツを収録。参加アーティスト<F/T09春秋>:ヘルガルド・ハウグ、ダニエル・ヴェツェル(リミニ・プロトコル) / イ・ユンテク / 高山明(Port B) / 松井周(サンプル) / 天児牛大(山海塾) / ロメオ・カステルッチ(ソチエタス・ラファエロ・サンツィオ) / 白井剛 / 井出茂太 / 蜷川幸雄 / さいたまゴールドシアター / 松田正隆(マレビトの会) / 平田オリザ、アミール・レザ・コヘスタニ、シルヴァン・モーリス / 飴屋法水 / 演劇/大学09春 / 伊藤キム。<F/T09秋>松本雄吉(維新派) / シュテファン・ケーギ、イェルク・カレンバウアー(リミニ・プロトコル) / 松井周(サンプル) / ブルーノ・ベルトラオ(グルーポ・ヂ・フーア) / 高山明(PortB) / 黒田育世(BATIK) / 飴屋法水 / クリス・コンデック / ラビア・ムルエ、リナ・サーネー / 天児牛大(山海塾) / タニノクロウ(庭劇団ペニノ)/ロメオ・カステルッチ(ソチエタス・ラファエロ・サンツィオ) / 伊藤キム / 快快。 | |||||||
| H1540 | フェスティバル/トーキョー10 ドキュメント | フェスティバル/トーキョー実行委員会 | フェスティバル/トーキョー | 2011 初版 |
\600 | 程度A-、帯 | \1,500 |
| ●“演劇を脱ぐ”最先端はここにある。物語、劇場…さまざまな既成疑念から脱し、現代都市、歴史への回路を拓くトーキョー発・舞台芸術の祭典、30日間のドキュメント。ロジェ・ベルナット/ジゼル・ヴィエンヌ/飴屋法水/高山明(PortB)/前田司郎(五反田団)/黒田育世/クリストフ・マルターラー/三浦基(地点)/ロドリゴ・ガルシア/松田正隆(マレヒトの会)/相模友士郎/ウェイ・ホイ、ウー・ウェングアン(生活舞踏工作室)/勅使河原三郎/平田オリザ+石黒浩研究室/やなぎみわ。 | |||||||
| H1769 | フェスティバル/トーキョー11 ドキュメント | フェスティバル/トーキョー実行委員会 | フェスティバル/トーキョー | 2012 初版 |
\600 | 程度A-~B+、帯 | \1,500 |
| ●「テーマ1 3・11以降 ―新たな現実を前に、演劇の想像力が試されている」「<関連作品>『宮澤賢治/夢の島から』 ロメオ・カステルッチ、飴屋法水/「トータル・リビング 1984-2011』 遊園地再生事業団/他」。「<シンポジウム> 司会:鴻英良:『3.11 以降の芸術活動とその公共性をめぐって』 近藤誠一×ハンス=ティース・レーマン×相馬千秋他。「テーマ2 「劇場」から都市へ ―そこに見出される新たな時間、風景、演劇」「<関連作品>『無防備映画都市―ルール地方三部作・第二部』 フォルクスビューネ/『風景画―東京・池袋』 維新派/他」。「テーマ3 アジアの同時代 ―公募プログラムに見るアジア舞台芸術の現在地」「テーマ4 未来へのアーカイブ ―アート/ジャーナリズム/アクティビズムの新地平」他。特別付録: 「宮沢賢治/夢の島から」 飴屋法水 「じ め ん」 上演台本。 | |||||||
| H1743 | フェスティバル/トーキョー12 ドキュメント | フェスティバル/トーキョー実行委員会 | フェスティバル/トーキョー | 2013 初版 |
\600 | 程度A-、帯 | \1,500 |
| ●座談会 ことばの彼方へ――イェリネクの演劇言語をめぐって――高山明(Port B)×三浦基(地点)×林立騎/世界の<現実>にアクションする・座談会 現実へのアクション――演劇が生み出す摩擦 マティアス・リリエンタール(世界演劇祭2014芸術監督/前HAU芸術総監督)×鴻英良(演劇批評家)×相馬千秋(F/T プログラム・ディレクター)/・ナンダン・アラデア(シアタースタジオ・インドネシア、F/Tアワード受賞者)インタビュー/・フランク・バウムバウワー(ミュンヘン・カンマーシュピーレ前芸術監督)インタビュー/・ジャン・ミシェル・ブリュイエール/LFKs『たった一人の中庭』 フォトレポート/<特別付録>エルフリーデ・イェリネク『光のない。(プロローグ?)』(翻訳:林立騎)『光のない。』『エピローグ?[光のないII]』との三部作として発表された新作をいち早く掲載! 他。 | |||||||
| H1688 | フェスティバル/トーキョー13 ドキュメント | フェスティバル/トーキョー実行委員会 | フェスティバル/トーキョー | 2014 初版 |
\600 | 程度A-、帯 | \1,512 |
| ●<シンポジウム>『演劇の未来』採録/ハンス=ティース・レーマン×シュテファニー・カープ×岡田利規×高山 明×ダニエル・ヴェッツェル×宮沢章夫(司会:林 立騎)。<座談会>・物語を旅する/岡田利規×小沢 剛×保坂健二朗×松井 周(司会:相馬千秋)・東京にはどんなフェスティバルが必要か/市村作知雄×内野 儀×相馬千秋×高萩 宏×林 立騎×平田オリザ×野村政之×三好勝則(モデレーター:吉本光宏)。<特集> フェスティバルが見せた「トーキョー」Port B『東京ヘテロトピア』、リミニ・プロトコル『100%トーキョー』。 | |||||||
| H873 | 加藤健一事務所Vol.45「審判」20周年記念公演プログラム | 加藤健一事務所 | 2000 初版 |
\400 | 程度A- | - | |
| ●2000年東京、新神戸、大阪、京都ほか全国16ヵ所上演した「審判」20周年公演プログラム。その中のひとつ、グリーンホール相模大野公演のミニ冊子付き。 | |||||||
| H1381 | 2006年新国立劇場「アジアの女」公演プログラム | 新国立劇場 | 2006 初版 |
\400 | 程度A- | \800 | |
| ●2006年新国立劇場で上演された「アジアの女(作・演出長塚圭史)」の公演プログラム。 | |||||||
| H1690 | 阿佐ヶ谷スパイダース「アンチクロックワイズ・ワンダーランド」公演パンフレット | 2010 初版 |
\400 | 程度A- | - | ||
| ●阿佐ヶ谷スパイダーズ2010年「アンチクロックワイズ・ワンダーランド」公演パンフレット、全78頁。作・演出:長塚圭史:池田鉄洋・内田亜希子・加納幸和・小島聖ほか。 | |||||||
| H1691 | 解散記念公演「笑う巨塔」と東京セレソンデラックスその全て 公演パンフレット | 2012 初版 |
\400 | 程度A- | - | ||
| ●東京セレソンデラックス解散公演2012年「笑う巨塔」の公演パンフレット「『笑う巨塔』と東京セレソンデラックスのその全て」全68頁。作・演出:宅間孝行:斎藤工・芦名星・駿河太郎・伊藤高史ほか。 | |||||||
| ▲新着本&再入荷紹介 |
| ▲トリスタン・ツァラとダダ |
| ▲アンドレ・ブルトンとシュルレアリスム |
| ▲コクトー/アポリネール/ジャリ/ルーセル |
| ▲アルトー/クノー/アラゴン/ドーマル |
| ▲マルセル・デュシャン/マン・レイ/ブラッサイ |
| ▲ロシア・アヴァンギャルド/ドイツ表現主義/バウハウス |
| ▲1920年代、30年代文化 |
| ▲1920、30年代を彩った女性たち(モダンガールズ) |
| ▲世紀末とベル・エポック |
| ▲寺山修司&天井桟敷 ▲唐十郎&状況劇場 (日本の演劇) |
| ▲つかこうへい ▲野田秀樹 ▲鴻上尚史 (日本の演劇) |
| ▲竹内銃一郎/岡部耕大/山崎哲/川村毅 (日本の演劇) |
| ▲渡辺えり子/如月小春/岸田理生/劇団「青い鳥」 (日本の演劇) |
| ▲北村想/高取英/小松杏里 (日本の演劇) |
| ▲別役実/清水邦夫(日本の演劇) |
| ▲斉藤憐・串田和美/岩松了 (日本の演劇) |
| ▲井上ひさし/筒井康隆(日本の演劇) |
| ▲松尾スズキ/宮藤官九郎/中島かずき「劇団☆新感線」 (日本の演劇) |
| ▲宮沢章夫/平田オリザ (日本の演劇) |
| ▲成井豊とキャラメルボックス/横内謙介/高橋いさを (日本の演劇) |
| ▲永井愛/高泉淳子/飯島早苗(自転車キンクリート)/柳美里 (日本の演劇) |
| ▲坂手洋二/鐘下辰男/大橋泰彦/鈴江俊郎 (日本の演劇) |
| ▲古城十忍/和田憲明/砂本量―/マキノノゾミ (日本の演劇) |
| ▲ケラリーノ・サンドロヴィッチ (日本の演劇) |
| ▲西田大輔 (日本の演劇) |
| ▲日本の演劇(劇作家別あ~か行) |
| ▲日本の演劇(劇作家別さ~た行) |
| ▲日本の演劇(劇作家別な~は行) |
| ▲日本の演劇(劇作家別ま~わ行) |
| ▲優秀新人戯曲集/新鋭劇作集 |
| ▲日本の演劇(評論・教本/俳優自伝/雑誌・ムック/ミュージカル/その他) |
| ▲演劇ぶっく・えんぶ |
| ▲外国の演劇/ダンス(外国編) |
| ▲劇書房・而立書房ー海外(外国)演劇・戯曲 |
| ▲海野弘 |
| ▲外国文学(英米・フランスその他の国々の文学及びSF・ノンフィクション等) |
| トップページへ戻る |